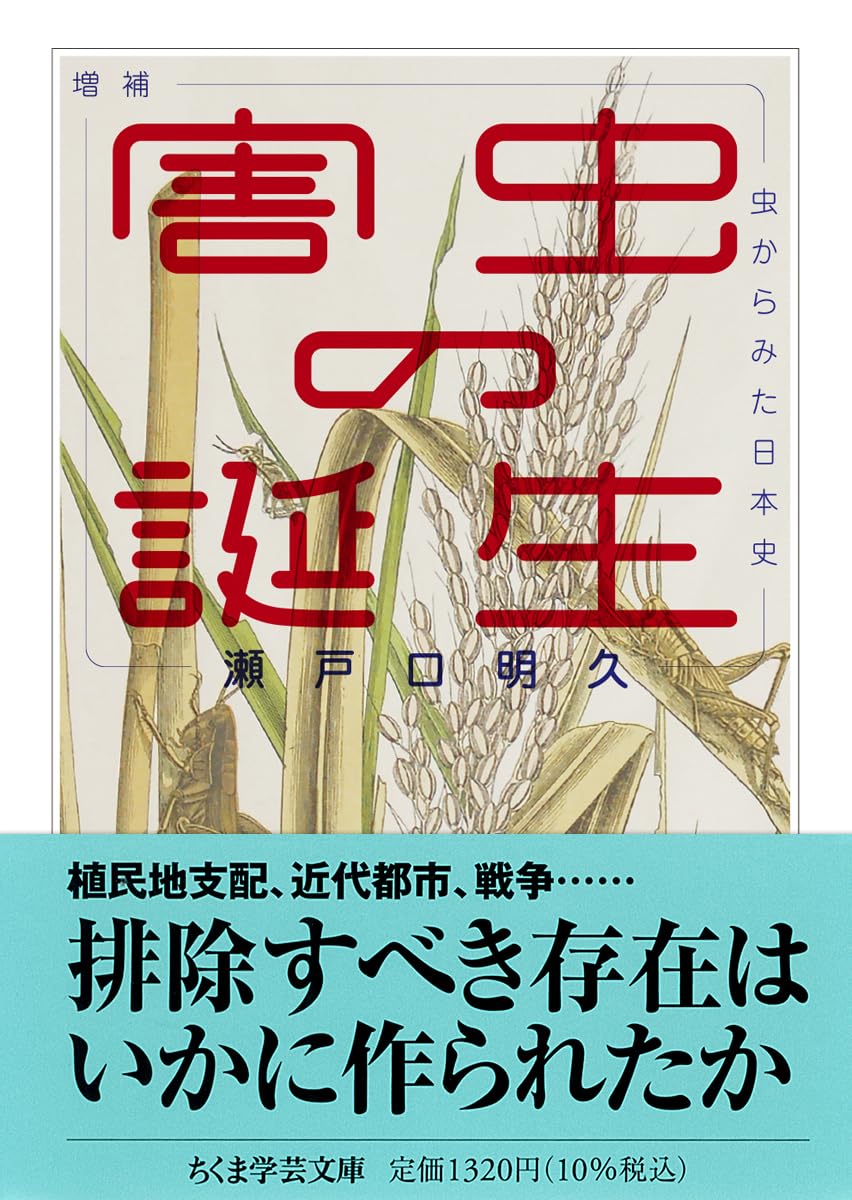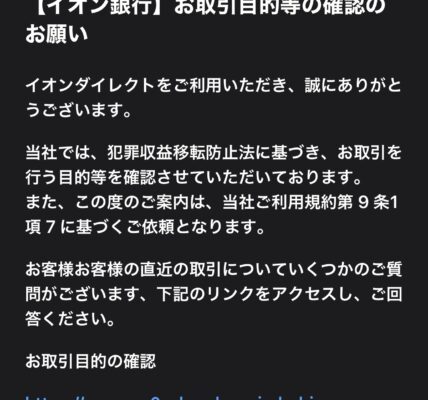「害虫」という言葉を耳にすると、多くの人がまず思い浮かべるのはゴキブリや蚊、ハエといった存在ではないでしょうか。台所や寝室に現れると不快で、時に病気を媒介する。それゆえに「害虫=駆除すべきもの」というイメージは現代社会に広く浸透しています。けれども、この「害虫」という概念は決して普遍的でも絶対的でもありません。むしろ人間の社会や文化、経済活動のあり方に大きく依存しているのです。ここでは、歴史的背景や地域ごとの違い、そして農業者と生活者の視点の差などを交えながら、その多面性を探ってみたいと思います。

そもそも、北海道の人間にとっては、珍しい存在であるゴキブリなんか、逆に興味関心の対象でしかなくて、それらの生息域に行くと積極的に写真を撮ってしまう自分なんかが語ってもアレなんですがね・・・
害虫とは一般に「農作物や森林、家屋、家畜、人間に被害を与える昆虫その他の動物」を指します。しかし重要なのは、昆虫そのものが本質的に「害」なのではなく、人間にとって都合が悪いときに初めて“害虫”と呼ばれるという点です。
歴史を振り返ると、古代エジプトや中国の記録には、イナゴの大群が農作物を食べ尽くす様子が残されています。中世ヨーロッパではペストを媒介するネズミやノミが「恐怖の害獣・害虫」として恐れられました。産業革命以降、大規模農業の発展とともに害虫被害は拡大し、19世紀から20世紀にかけては化学農薬の登場によって「害虫=排除対象」という考えが強まります。ところが20世紀後半以降になると、環境保全や持続可能性の観点から「完全駆除」から「総合的管理」への転換が進みました。このように、害虫観は常に社会のあり方とともに変化してきたのだろうと考えられますね。
そしておそらく同じ「害虫」でも、農業経営者と一般生活者ではその捉え方が大きく異なります。
農業経営者にとって害虫は、直接的に経済的損失をもたらす存在です。1匹2匹ではなく、群発的に発生して収穫量や品質を落とすことが最大の問題となります。防虫ネットや農薬、天敵利用などの管理はコストそのもので、害虫は「経営資源を奪うリスク」として扱われるはずです。ここには「ゼロにすることは不可能だが、被害をコントロールする」という現実的な姿勢が見られます。
一方、一般生活者にとって害虫は主に「不快さ」や「衛生上の不安」と結びつきます。ゴキブリや蚊は「経済被害」よりも「嫌悪感」や「病気の媒介」という側面で恐れられ、一般家庭であれば1匹でも家に出れば大騒ぎになることも少なくありません。つまり、農業者が「管理すべき自然現象」として害虫を捉えるのに対し、一般生活者は「排除すべき侵入者」として受け止める傾向が強いといえそうです。
さらに視野を広げると、国や地域によって「害虫」の意味合いは大きく変わります。典型的なのが昆虫食の文化です。

タイやカンボジアなどの東南アジアでは、屋台で揚げたバッタやカイコのさなぎが普通に売られています。アフリカの一部地域では、サバクトビバッタやシロアリの群飛が農作物に被害を与える一方で、人々はそれを大量に捕獲し、栄養源として食べます。メキシコではトウモロコシ畑のバッタ「チャプリン」やアリの幼虫が伝統的な食材として根付いています。日本だって長野県などではそれなりに昆虫食文化が見られます。
これらの地域では「害虫=敵」ではなく、「害虫=資源」としての認識が強いのです。つまり同じバッタでも、日本の農家にとっては害虫、アフリカの村人にとっては食糧、研究者にとっては実験材料、都市生活者にとっては未来食材。まさに立場によって意味が変わる存在なのだといえそうです。

現代社会では「害虫」をどう位置づけるべきなのでしょうか。ここで役立つのが「害虫の三つの顔」という視点です。
1 .敵としての害虫:農業や衛生に損害を与える存在。駆除や管理の対象。
2 .不快存在としての害虫:都市生活者が心理的に忌避する存在。ゴキブリや蚊が代表。
3 .資源としての害虫:食材やタンパク源として利用できる存在。昆虫食や養殖飼料、さらには医薬研究にも活用。
⠀この三つの顔は、状況や文化によって比重が変わります。日本の都市部では「不快存在」としての側面が強調され、農村では「経済的リスク」としての意味合いが強い。昆虫食文化を持つ地域では「資源」として評価される。こうして害虫の概念は、人間と自然との関わり方を映す鏡であるといえそうです。
「害虫」という言葉を口にした瞬間、私たちはその生物にネガティブなラベルを貼っています。けれども実際には、害虫もまた生態系の一部であり、分解者や他の動物の餌として重要な役割を担っています。未来の食糧危機を考えたとき、今「害虫」とされている存在が、持続可能な社会を支える資源に変わるかもしれません。
つまり「害虫」とは単なる生物学的な分類ではなく、人間社会の価値観によって形作られる相対的な概念なのですね。敵でもあり、不快でもあり、資源でもある。この多面的な存在をどう受け止めるかは、私たち自身の文化や社会の姿勢を映し出しています。
ちなみにこの感覚は「雑草」にだって当てはまります。自分は猫のために散歩の途中でエノコログサを取って帰ることが多いですが、これも多くの人にとってはただの雑草です。(ちなみに今打ち込んで初めて知りましたが「エノコログサって狗尾草」って書くんですね。)
ということで、何を書いているかというと、昨日のクスサンで色々考えているところに、北大の知り合いが超絶面白そうな講義の話を書き込んでくれていて、気になりまくっていたのです。残念ながら講義に参加することはできませんでしたが、めちゃくちゃ面白そうな本を紹介していただいたので、早速購入し「読む前に自分の考え」をまとめておくためにというメモですw