北海道大学構内で見つかった“バイカルハナウド” —— 遷移の学習とリアルな課題がつながる瞬間
「先生、北大のニュース見ましたか?あれ、やばくないですか?」
北海道大学キャンパス内でセリ科の大型植物、「バイカルハナウド(Heracleum sosnowskyi)」が発見されたというニュースです。ロシア原産の外来種であり、欧州では深刻な侵略的外来植物として知られている存在だった。
ちょうど授業では植生の遷移を扱っています。裸地に始まり、草原、低木林、そして極相林へと至る過程。生徒たちは日本の代表的な植生遷移をこの後展開する予定でしたが、このニュースは使わない手はないということで準備してあったのでバッチリです。教材としてこれ以上ないリアルな素材だった。

ちなみにこれだという話でしたが、これはその辺にいくらでも生えている「ノラニンジン」という種類です。まあ、同じ科ですから、同じような花なのは納得ですけれど・・・
「なぜ流入したのか?」最初に投げかけたのはこの問いです。
「このバイカルハナウド、なぜ北大に現れたのだろう?」自分なりの仮説をどんどん展開してくださいという話にしてあります。
「海外の研究者によって持ち込まれたのでは?」「園芸目的?研究用?あるいは種子の混入?」「温暖化によって生育域が変化している」「旅行者の荷物とかについてきたのか」「実は今まで発見されていなかっただけで今までもあったのかも」「鳥などに運ばれてきたのかも」
生徒たちは地図などを参考に種子の広がり方を考えていました。個人での作業にしたのですが、「こういう考え方もできない?」と新しい考えが浮かんだら大きな声で言ってしまうのは「アピールしたい」気持ちの現れなのでしょうね。
一つの植物が出現した背景には、人の移動・物流・気候変動が絡み合っている。その複雑さを“実感”として捉えた瞬間だった。
「どう処理すべきか?」という問い
次に考えてもらったのは、このバイカルハナウドをどうするかということ。
・すぐに駆除すべき?
・本当に広がっていないならその駆除のみで
・駆除するにもどんな手法があるの?
・そもそも、在来種にどんな影響が?
ここで生徒たちは、自分たちの知識の“穴”にも気づいていった。植物の繁殖戦略、土壌改変、他種へのアレロパシー的影響…。
駆除と言っても、一つひとつが科学的根拠をもって選ばれるべきだということが、彼らなりに理解できてきたようだった。ただ、先ほどの問題でも関わるがあるのでしょうが「花粉が飛んできて広がった」とか「花粉を飛ばさないように」という記述も見られたので、「種子と花粉」または「種子と胞子」の混同が有るのかも知れないなと思いました。
たった一株の外来植物が引き起こした、教室外での探究の連鎖。
「教科書で習うこと」が、「いま・ここ」で起きていることと地続きになった。生物基礎の授業が、知識を“暗記するもの”から“使って考えるもの”へとシフトする、そのダイナミックな瞬間であれば良いなと感じました。
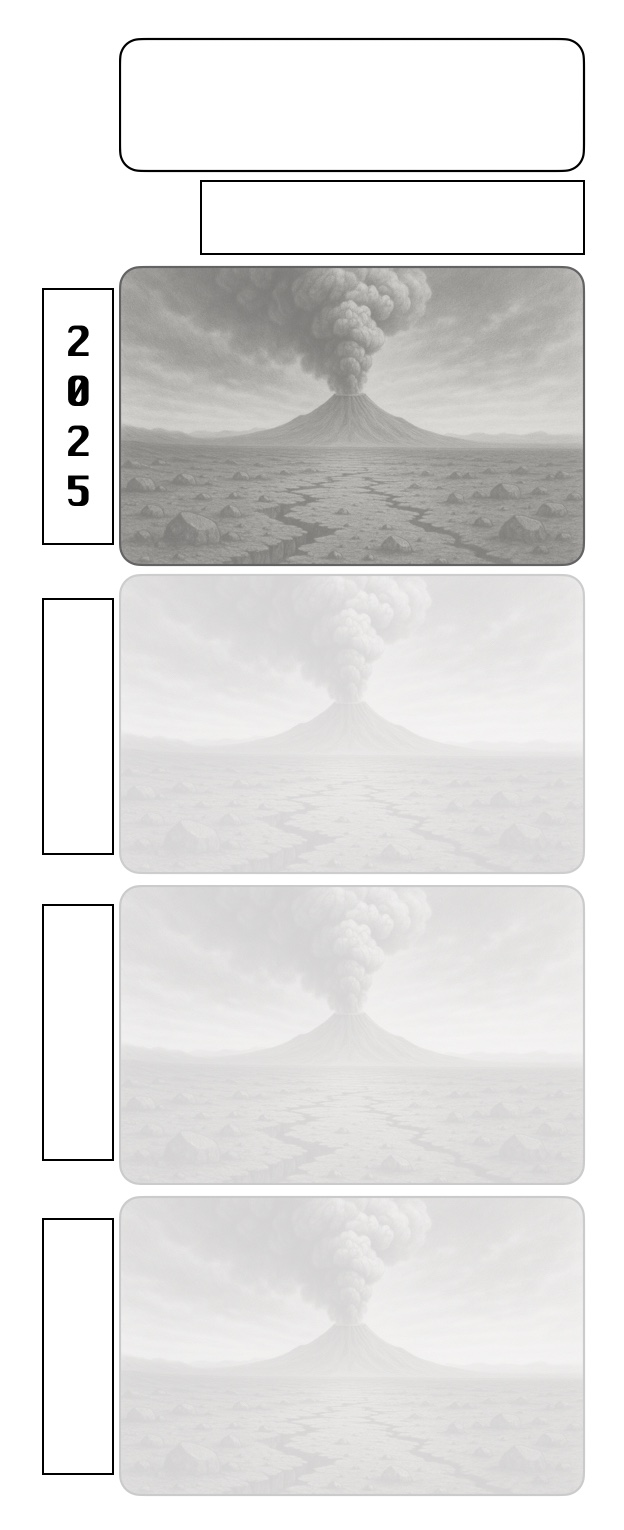
次の時間からは小笠原の「西之島」を軸にして、この後どのような植生変化が起こるのだろうかというのを進めていく予定です。
自然科学ランキング




